
良書吉日②読書案内「徳川慶喜が天皇に政権を返上した大政奉還までのおよそ270年間」
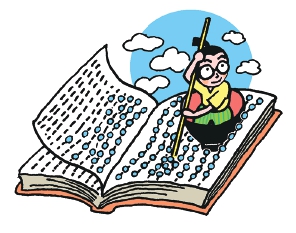
『将軍の世紀』山内昌之著(文藝春秋刊)
今回は大冊。上巻735頁、下巻760頁、合わせて1495頁の大分量。
本書は1600年、徳川家康の関ケ原合戦から幕末1867年徳川慶喜が天皇に政権を返上した大政奉還までのおよそ270年間を扱っている。これは、徳川政権が中世の分裂を克服して日本を「一つの国家」に近づけパクス・トクガワナ(徳川の平和)と呼ばれる長い時代であった。一国家が整備されるとともに民間社会が成熟し、日本列島の均質化が進んだ時代である。
著者の山内昌之氏は、イスラム、ロシア、中東の歴史学的研究の第一人者であり、その山内氏が江戸時代について書いたのである。大量の文献史料の収集と研究で読み応えのあるものになっている。

徳川将軍十五代はどのようにつながっていったのか。家康、秀忠、家光、家綱の四代までは父子相伝で、家綱に子がないため弟綱吉が継いだが、また男子がいないため甥の家宣、その子の家継へとつながった。しかし、家継に子がなかったため紀州家から家康の曾孫の吉宗が入って八代を継承する。
八代将軍吉宗は家重、家治の父子三代で終わり、十一代の家斉は吉宗のつくった一橋家から出てつながった。家斉、家慶、家定は父子相伝だが、家定で絶え、家斉の孫にあたる家茂が紀州家から入って繋がった。
ところが、十五代慶喜は家康の十一男頼房を祖とする水戸家の子孫であり、ここで正統からすこぶる血が薄くなるが、宗家を継ぎ将軍になった。
これら将軍の政権は、徳川宗家のみに政治基盤を置く政権であり、将軍が自ら考えて決断できる政権であった。ことから、老中、若年寄を頂点とする官僚行政機構の決定に頼らなかった。しかし、一方、近世にあたる江戸時代は、現在の東京、つまり江戸が事実上の首都として繁栄し、各藩の自立した内政によって地方も豊かに成長した時代でもあった。このおよそ270年間が、その後の日本を形づける原型になったのでる。
■吉法師
漁師町の生まれ。青春は陸上競技に明け暮れ、その後、トライアスロンにも挑戦。中学生時代、国語教師への憧れから、読書に目覚め、今や本の虫。
この記事を書いたライター
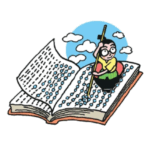



-1s-212x300.jpg)