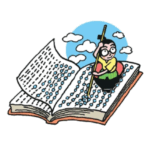良書吉日③読書案内「読み進むうちに謎解きにも似たワクワク感」
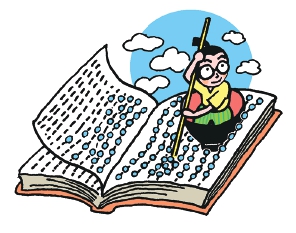
『古代国家はいつ成立したか』都出比呂志著(岩波新書)
日本において国家はいつ成立したのだろうか。またそれは、どのような過程を経て生まれたのだろうか。日本の古代を中心に研究してきた考古学者の著者がそれを解き明かしてくれる。読み進むうちに謎解きにも似たワクワク感が湧いてくる。

1989年佐賀県吉野ケ里遺跡、1995年大阪府池上曽根遺跡がそれぞれ発見された。いずれも弥生時代中期の巨大環濠集落の遺跡である。この弥生時代には水稲農業が始まり、土地と水をめぐる紛争や石器や鉄器などの資源をめぐる争いが始まった。この環濠は集落の平和を脅かすものへの防御施設となった。
そして、邪馬台国や卑弥呼について文字で書かれた『魏志倭人伝』である。この『倭人伝』がなければ邪馬台国という国の存在も、卑弥呼という女王の名前も全く知られないままであった。邪馬台国の下に国々が統括されていった。古墳時代になると地方の首長は中央政権の下で権力構造に組み込まれ、身分が定まっていく。その身分が古墳の形と大きさで表現された。
ところが、四世紀末から五世紀初頭にかけて、古墳の動向に大きな変化が起きてくる。それまで前方後円墳を代々築いてきた首長たちが古墳を築かなくなったり、円墳しか作らなくなったりした。
権力の変動により、権力継承のシンボルであった前方後円墳は祭式の意味を失い、消滅へと向かっていく。同時に、中央権力が地方権力を飛び越して直接人々を掌握するように変貌していく。
初めて律令制が敷かれたのは七世紀といわれる。身分制度、官僚制度、国家による土地の占有、軍制など律令国家は古代国家として成熟したものである。
本書は、私たちのたどってきた足跡が踏み固められて、社会が成長していく様を眼前に拡げてくれる。
■吉法師
漁師町の生まれ。青春は陸上競技に明け暮れ、その後、トライアスロンにも挑戦。中学生時代、国語教師への憧れから、読書に目覚め、今や本の虫。
この記事を書いたライター