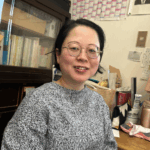私の不登校、言い換えると?

不登校生が増え続け『不登校』という言葉が市民権を得つつあります。私が小学生のころは『登校拒否』という言葉が主流でした。登校を拒否する。クラスに一人いた学校に来ていない子について、「あの子は学校に来たくなくて来ないんだなあ」と子どもながらに認識した記憶があります。
90年代後半、学校基本調査で『学校ぎらい』という区分が『不登校』に名称変更されたことをきっかけに『不登校』という言葉が主流になっていきました。この変更には、「学校に行かない(行けない)のは必ずしも子どもの意志によるものだけでなく、学校や家庭などさまざまな要因によって生じる状態である」と訴える、当事者や関係者の運動があったということです。
学校に、明確な意志を持って行かない子、行きたくても行けなくて揺れている子、自分がどんな気持ちか分からない子…。学校に行っていない状態は同じでもその内実は千差万別です。そういう意味で『不登校』は包括的な表現と言えます。
現代の当事者たちはどのように感じているか、ゆうびの若者たちと話し合ってみました。
◆知さん(20代)「自分は小学生から不登校で勉強もしてこなかったけど、今になって勉強したくなってきて、本を読んだり歴史を調べたりしてる。今が私の学びのタイミングだったんだと思う。『タイミング待ち人』というのはどうだろう」
◆厚さん(30代)「自分で行く曜日を決めて行っている子がいて、自由でいいなと思う。『マイスタイル登校』という感じ」
◆潤さん(20代)「『選択的自由学習』とかよく言うけど、僕はあまり好きじゃない。僕は行きたくても行けなかったから。別に選んだわけじゃないから」
◆里さん(小学生保護者)「うちの子は『ザ・登校拒否』と言う感じ。でも学校の先生に『うちの子、登校拒否で~』と言うのはちょっと言葉が強いかな」。
どの言葉も不登校生全員の内実を表現するには言葉足らずです。でも、一人ひとりの不登校生が自分を表現する言葉を考えるのは、自分や学校について、理解を深めることになるでしょう。
この記事を書いたライター